

ゲームが教育を変える!ベアラボの新しい研修アプローチとは
ゲーミフィケーションが教育に革命を起こす
教育とゲームの融合、いわゆるゲーミフィケーションの重要性が高まる中、株式会社ベアラボはその先駆者として名を馳せています。最近のプレスリリースでは、彼らの未来に向けた夢と挑戦が語られ、教育現場でのゲームの役割が新たな光を浴びています。
“教育”と“ゲーム”の融合
「研修はいつもつまらない」と感じている人は多いでしょう。此れを打破するために、ベアラボは「受けたくなる研修」や「話題になる学び」を提供することを目標としています。彼らの理想は、ゲームを通して学ぶことが一般的になる未来です。そのためには、受け身の学びから抜け出し、自らの言葉で思考し、仲間と対話しながら行動へつながる「自分ごとの学び」を実現する必要があると、彼らは考えています。
現場の実体験をゲームで再現
ベアラボが提供する研修用のゲームは、単なる娯楽ではありません。彼らが目指すのは、現場でのコミュニケーションや意思決定のプロセス、チーム内の重複や混乱を安全なゲーム内で体験することで、実際の職場環境を反映したシミュレーションです。このような体験を通じて、参加者は自身の行動や思考の偏りに気づき、より良いチームワークを築く能力を向上させることが目指されています。
例えば、意見が食い違う理由や、指示が曖昧になりやすい構造、役割の混乱が引き起こす問題などをゲームの中で体感することで、現実の職場での課題にも直面させます。「いつの間にか、自分のクセが出ていた」という参加者の声は、学びの深さを示しています。
高い効果を目指す研修設計
ベアラボでは、体験型の研修に心理理論や組織的視点を取り入れています。彼らは、単に「楽しい」と感じる研修では終わらず、実際に行動や変化を生むためのプログラムを設計しています。これにより、学びが個々のビジョンに実用的に結び付くことを重視しています。
効き脳(思考スタイル)
人それぞれが異なる「思考のクセ」を持っていることをベアラボは重視しています。彼らは、ハーマンモデルに基づいて、論理・計画・感情・直感の4つに思考スタイルを分類することで、職場でのすれ違いの原因を可視化し、参加者に気づきを与えています。
SSR理論
組織が機能するためには、強み・仕組み・関係性の3つの要素が必要であるとベアラボは説いています。この考え方に基づき、個人の努力だけに頼らず、全体的な構造から人材育成へとアプローチすることで、持続可能な組織づくりをサポートしています。
ベアラボの普及活動
ベアラボは、ゲーミフィケーションに基づいた研修のリーディングカンパニーとして、職場における「学びの場」を体験と対話を通じて設計・提供しています。設立以来、多様な業界で研修を行い、企業の変革と成長を支え続けています。彼らのWebサイト(ベアラボ公式サイト)を訪れることで、彼らのビジョンや研修の具体的な内容についてさらなる情報を得ることができます。
教育とゲームの融合は、単なるトレンドではなく、未来の学びの形として確実に進化を遂げています。ベアラボの挑戦から目が離せません!

関連リンク
サードペディア百科事典: ゲーミフィケーション 教育 ベアラボ
トピックス(その他)




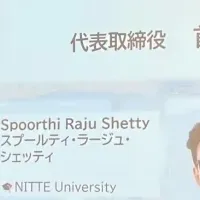

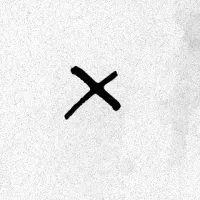

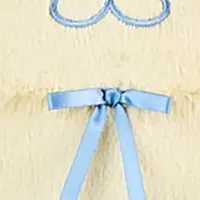

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。